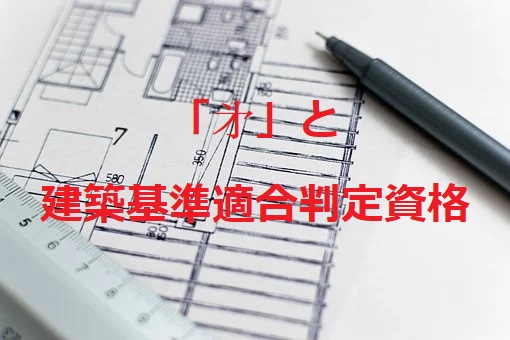建築基準適合判定資格者検定(建築主事試験)の試験勉強お疲れ様です。
主事試験の考査Bの解答は試験元より発表されておらず、書き方について様々な噂などが出回っています。
今回はその中で、考査Bで多く書かなければならない法第何条の「第」について略字である「㐧」を使用してよいのか、また省略してよいのかについて書いていきたいと思います。
略字とは
まず略字についてです。調べると「本来の事態から省略・変形をしたもの」を言うそうです。
ほかにも俗字や異体字ともいわれているそうですが、詳しくは調べてもよくわかりませんでした。
今回は細かい定義は別にして、「第」の略字は「㐧」ということで話を進めていきます。
考査Bに略字を使用してもよいのか。
主事試験を受けることを職場の合格者の先輩に伝えると、まずもらえるアドバイスというものがいくつかあります。
「考査Aは満点取れよ。」「考査Bの道路斜線は捨てていいぞ。」「第は略字(㐧)を使え。」
など皆さんも言われた経験があるかもしれません。
結論から申します。
建築基準適合判定資格者検定において略字である「㐧」は使用しても受かります。 筆者含め、周りの話を聞いた人は全員使用していました。
正直こんなに経験者がいて、合格者もいるのに、毎年略字を使用していいのかという話題になります。
受験生のほとんどが使用している『建築基準適合判定資格者の手引き』を発行している建築行政情報センター(ICBA)が毎年行っている講習会にて、その質問もほぼ毎年挙がっているような気がします。
その質問への解答としては、「試験元ではないので答えられない。解答例に沿って正しく書くべき」といった回答がされています。
たしかに根拠規定を各一番右側の上には「(例)令第〇条第〇項第〇号」と書いてあるので、その通り書くのが無難ではあります。
「第」は省略してもよいのか
続いてより攻めた書き方になります。
そもそも「第」の文字を書かず「令〇条〇項〇号」と書くとどうなるかということですが、ここまで省略した人に会ったことがありませんので、わかりません…。
正直解答例には反した書き方になりますが、条文を指定することはできているので、問題なさそうに思えます。
ですが1年に1回しかない試験で自分の将来がかかったものになりますから、そこまで攻める必要はないと思います。それよりも問題演習をして時間を生み出すことに重点を置くべきです。
それでも合格した人がいればご連絡お待ちしております。
また、それ以上省略すると、条文の指定ができなくなります。
例えば「令108条-2」といった‐を使った省略をすると、令第108条第二号なのか令第108条の2なのか区別することができません。
おそらくここまで省略する人はいないと思いますが、採点官の人が見たときにどう捉えられるかといった思いやりの精神を持つことは文字を書く試験においては重要だと思っています。
一級建築士試験においても、試験官に好印象を持たれるような図面の作図に注力していたと思います。
主事試験においても、「この字だと読みにくくないかな」「根拠理由が伝わるかな」といった思いやりの心を大事にして試験勉強に励んでいただければと思います。
まとめ
今回は主事試験の毎度の噂、略字について話してきました。
結論、略字を使用しても合格はしますが、減点されているかもわかりませんし、今年度より採点基準が変わるかもしれません。
あくまで筆者の体験談として捉えていただき、参考にしていただければと思います。
略字の使用は自己責任です!
今回もご覧いただきありがとうございました。